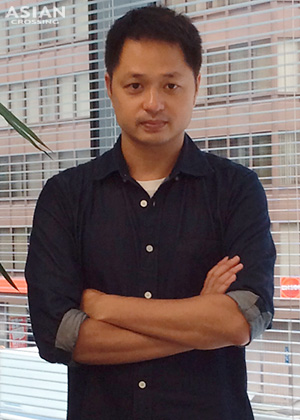

監督だけでなく俳優業も好き!と語るチェン・ヨウチェ監督
(日本語が堪能なので日本作品もOK!)

|
●守りたいアイデンティティ
Q:この物語は原住民の話として作られているけれども、台湾自身が抱えている問題にも当てはまるとおっしゃっていますが、具体的にはどういう問題があるのですか?
監督「台湾を1つの村とみたら、まったく同じなんです。今、台湾は自分が誰かっていうアイデンティティを探しているのに、外国からの資金、資本が入って来くると、自分のものを全部売ってしまう。すべてをお金に換えてしまう。そういうところは、まったく同じなんです」
Q:何かを失くしていっている?
監督「そう。土地でも、どんどん外国の資本が入って来て、台湾の土地を買っているし、仕事のために家族と生活できなくて、中国に渡って仕事をしている人々がいて、そういう家族がすごく普通に、たくさんあるんです。今の大学生は、卒業したらまず中国へ行くか、と。それくらい、台湾を離れていってしまう。あっちの方がぜんぜん就職の条件がいいから。資本も多い、チャンスも多い。だから、皆、あっちへ行っちゃう。それで結局、台湾は村みたいに、年寄りと子どもしか残らない。台湾を1つの村とみると、その現状がまったく同じなんです」
Q:もう一度、台湾にちゃんと目を向けてみようというメッセージですね?
監督「そうですね。一番大事なものは何か。それと、子どもたちに何を残していくか。このまま全部売ってしまったら、何も残らないから。お金だけが残っても、お金はいずれ使っちゃう。気がついた時には、自分の土地がない、自分の言葉もしゃべれない。自分の名前すら忘れてしまう。台湾は未だに、自分が誰かということが大きな声で言えません。国際社会は皆、台湾のことを見て見ぬふりをする。無視されてる。それは、台湾の中の原住民においても同じなんです。原住民映画、原住民に関しては、見て見ぬふりをすることが多い。だから、僕はまったく同じだと思うんですよね」
Q:日本で公開される台湾映画を見ていると、台湾人とは何か、台湾らしさとは何かを追求している作品が多いですね。
監督「台湾はまだ、それが確立されていない。だからこそ、皆、それを追求してるんです」
もどかしい思いを、監督は熱く語ってくれました。


親から子へ、祖父から孫へと、伝統文化と大切な思いが受け継がれていく。

(c)一期一會影像製作有限公司
●実は監督より俳優業が好き?!
Q:監督ご自身について、お聞きします。映画監督をめざしたのは大学の頃だそうですが、最初は経済を勉強されてます。その頃から、映画をやりたかったのですか?
監督「映画は小さい頃から好きでした。大学の時に、初めて映画祭というものを見て、こういう映画ってあるんだ、映画ってこういうことができるんだ、とういことを初めて知って、自分でも作りたいと。若い文芸青年によくあるようなパターンですけど。後……、かっこいい!(笑)『僕は映画作ってる』って言うだけでもかっこいいと、文芸青年気どりだった(笑)。それは最初の頃ですけど。
経済もやりました。経済っていうのは目に見える価値を計算する学問ですよね。でも、この世には数字にできない価値というのがたくさんあると、僕は未だに信じてる。そうやって信じてきた方が、生きていて、僕は楽しい。だから、経済を習った上で、これが世の中の仕組なんだと、世の中の大体の経済の仕組、政治の仕組、国際社会の仕組はこういうやり方なんだとわかった。でも、それ以外にもっと大切なものがある。僕はそれを、そっちの方をやりたいと思った。だから、別に裏切ってるわけじゃないですよ(笑)」
Q:両方とも大事ですよね。映画を作るにはお金も必要ですし。
監督「そうです。そういう、形にできるものと、形にできないものは、対立しているように見えるけど、神や仏様の目から見たら同じなんですよね。んー(と、言葉を探して、言いたいことの適切な表現がみつからなそう)…まあ、僕はわがままにやりたいんです」
Q:演じるのと監督するのと両方やってらっしゃいますが、監督の方がお好きだとは思いますが、俳優もけっこうやって…
監督「いや、俳優の方が好き(笑)。でも、雇ってくれない。誰も(笑)」
Q:えー?! ドラマもたくさん出てますよね?
監督「今はない。今は誰も声をかけてくれないから、し方なく映画監督をやってます。じゃなくて(笑)。もちろん、声をかけられてないのもあるけど、僕は面白い映画を作って、面白い映画を産み出す方が面白い。そっちの方がやりがいがある時が多い。でも、仕事としては、俳優の方が…なんていうかな…俳優の仕事でしかない面白みもある。それも好きなんです。ただ、あんまりチャンスがない」(冗談でよかった。でも、俳優業も好きなんですね)
Q:外国の映画に出てみたいというのはありますか?
監督「はい。(でも今は)お金がないからお願いしますっていう感じで、台湾の若手監督の映画に出させてもらってる(笑)」
Q:でも、有名な監督さんの映画にもちらっと出てますよね?
監督「そうですね。それはもう、声をかけられたら、はい!って。大体スタッフが同じなんです。『太陽の子』でも『KANO』でも、スタッフのリストを見たら大体同じ。台湾で映画をやっている人は一握りだから。大体同じような人がやってて、皆、僕が俳優をやりたがってるのを知ってて(笑)。だから、スタッフの方から声をかけられる」
Q:最近はお医者さんの役が多いと思いました。
監督「そうですね。ワントン(王童)監督の作品(『風の中の家族』)とか、『一分間だけ』(チェン・フイリン監督)」
Q:エンターテイメントの映画にも出てみたいですか? たとえばアクション映画とか。
監督「声をかけられたら絶対に行くけど、声をかけられてないから(笑)」
Q:ジョン・ウー監督の映画とか、そういうものにも出てみたい?
監督「はい。いや、でも…ジョン・ウーは僕の存在すら知らないと思う(笑)。だからまあ、無理しないで、チャンスがあれば絶対やります(笑)」
監督業と俳優業をこなすチェン・ヨウチェ監督のお父さんは日本育ちの華僑。お父さんと会話するために、幼い頃から日本語を教えられていた監督は日本語が堪能です。
同時に、アイデンティティの問題にも直面。前作の『ヤンヤン』ではフランス人とのハーフである少女ヤンヤンの葛藤が描かれています。走ることで自分自身を取り戻すヤンヤンと『太陽の子』のナカウ。偶然とはいえ、やはり似てますね。
|  |

|
●ディーン・フジオカと仕事をしたい
Q:日本の映画はどうですか? 日本語もできるし。
監督「日本で何か撮りたい、もしくは、日本の映画を作っている人と一緒に何かやりたいという気持はあります。僕も日本の小説はほとんど読んでて」
Q:映画化したい小説はありますか?
監督「ほとんどもう映画化されちゃってるし(笑)、これは!と思ったものはほとんど映画化決定と、調べたら出て来るんですよね」
Q:ドラマも撮ってますよね?
監督「ミニドラマ。あまり長いのはちょっと無理」
Q:日本の俳優さんと一緒に仕事をするというのは?
監督「もし、機会があれば。そうですね…ディーン・フジオカは台湾にいた頃の知り合いだったんです。ずっと一緒に仕事をするチャンスもなくて、日本に帰っちゃって。結局、日本で今…」
大ブレイクしています。
監督「そうですよね」
惜しかったですね。もうちょっと前だったら
監督「いや、でもまあ、それはそれでいいんじゃないかな」
今は忙し過ぎて、ちょっと難しくなったでしょうか?
監督「いや、大丈夫ですよ。大丈夫」
そうですね。きっと、ディーンだったら出てくれますよ。
監督「そういうチャンスがあれば、もちろん。彼は台湾にいた頃から、すごく勉強家というか、あの時は台湾で必死にギターの練習とか、曲を作ってたり。常に何かに没頭しているような方なんです。彼は実は、努力家なんです」
ぜひ、合作をしてください。
監督「もし、機会があれば」
Q:次回作はもう撮られていますか?
監督「2ヶ月後に撮ります。レカル監督は、今撮ってます。僕は2ヶ月後にミニドラマを撮ります。『他イ門在畢業的前一天爆炸』というミニドラマがあって、5年前に撮ったやつですけど、それの続き。5年経って、高校生がもう大学生になって、社会に入る頃の続きです」
それは面白そうですね。楽しみにしています。今日はありがとうございました。
ということで、ドラマも映画も今後が楽しみなチェン・ヨウチェ監督でした。ディーンの話が出て驚きましたが、ぜひ合作が実現することを祈っています。この日はたくさんの取材を受けた後で、台湾文化センターでのプレミア上映会に出席。上映前に舞台挨拶があり、上映後にはトークイベントも開催されました。


上映前のフォトセッション (c)台湾映画同好会
|  |


上映後はジャーナリスト野島剛さんとトーク
|


観客の皆さんをバックに記念撮影 (c)台湾映画同好会
|  |


修了後はロビーでサイン会も
|
『太陽の子』の日本上映プロジェクトは始まったばかり。本作には、現地の人々だけでなく、ウェイ・ダーション監督の『セデック・バレ』(11)で花岡一郎を演じたシュー・イーファン(徐詣帆)、『KANO〜1931海の向こうの甲子園〜』(14)でショートの上松くんを演じたジョン・ヤンチェン(鐘硯誠)も、重要な役柄で出演しています。また、第52回台湾金馬奨で最優秀オリジナル映画主題歌賞に輝いた主題歌「不要放棄」を歌っているのは、先住民のバンド、トーテムで知られるスミン(舒米恩)。彼は音楽も担当しています。9月には『太陽の子』ウィークと称して、主演のアロ・カリティン・パチラルさんを招いての連続上映イベントを開催。9月10日から19日まで、東京、静岡、神奈川、福岡でのリレー上映が予定されています。(詳細は右記)青い海と降り注ぐ太陽の光に祝福された、美しい田舎町での一人の女性の奮闘物語と爽やかな感動を、ぜひ劇場で味わってください。
(取材:2016年6月24日 台湾文化センターにて単独インタビュー)
前頁を読む P1 < P2 ▼『太陽の子』作品紹介
|